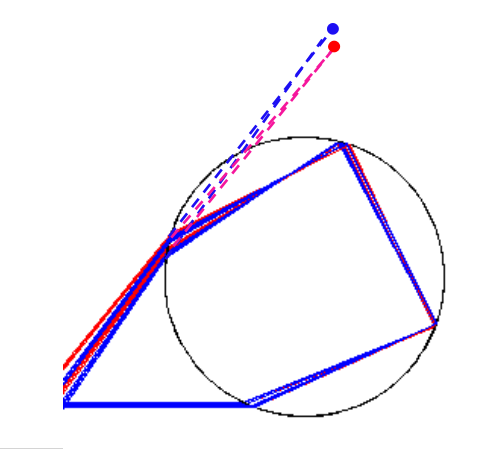概要
虹は観測者の後方に光源(太陽)があり、前方に水滴の壁があるときに見えます
虹は水滴の壁の表層で発生します
虹は主虹と副虹があり、各々どのような原理によるか記載します
主虹

主虹と副虹

主虹
❍ 主虹の発生原因
主虹は水滴に入射する光線の「屈折→反射→屈折」した光線です
下左図に水滴に入射した光線の様子を示します
ピンクの光線は拡散していますが、緑の線は拡散せずに射出しているのが分かります
この拡散せずに射出される光線が主虹として観察されます
※ 拡散する光線は目に届き難いので、知覚できません
※ 入射光線と拡散せずに射出する光線の角度は約40°です
下右図は下左図に示すディテクター(検出器)のエネルギー分布を示します
上5本の光線束(ピンク)は拡散し、最下部の光線(緑)は拡散していない様子が確認できます


❍ 色分解の原因
下左図は短波長(青)、中波長(緑)、長波長(赤)の光が水滴に入射した状態です
短波長の光は屈折角が大きく、長波長の光は屈折角が低いので入射端、射出端で色分解が生じます
下左図の青枠は射出端の拡大図ですが、赤に対し青が大きく屈折する様子が確認できます
下右図は僅かに離れた箇所に2本の光線が入射した状態です
観察者から見ると、その2本の光線の延長線上の接点に発光点があるよう観察されます
※ 主虹において、長波長の光が外側、短波長の光が内側に見えます
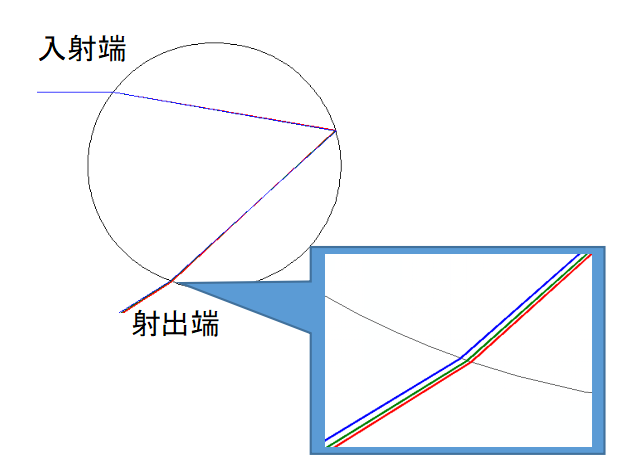
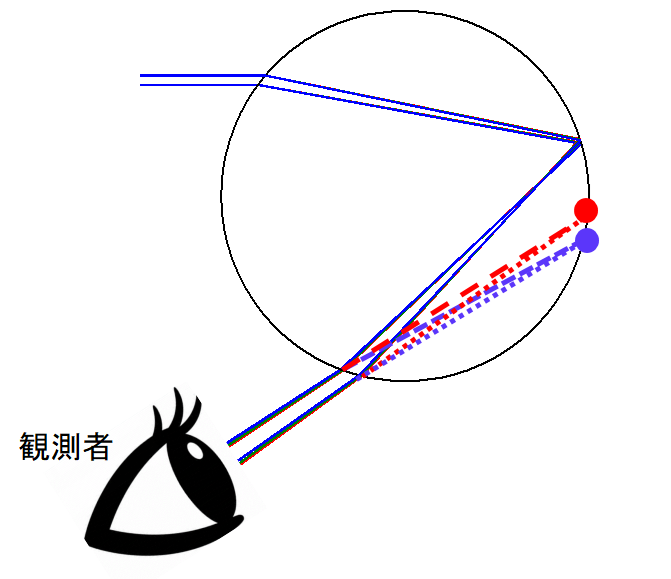
副虹
❍ 副虹の発生原因
副虹は水滴に入射する光線の「屈折→反射→反射→屈折」した光線です
※ 副虹は主虹と比較し反射回数が1回多いです
反射率は1回当たり約3.2%なので、主虹と比較すると明るさはおよそ1/ 30程度になります
下左図に水滴に入射した光線の様子を示します
ピンクの光線は拡散していますが、緑の線は拡散せずに射出しているのが分かります
この拡散せずに射出される光線が副虹として観察されます
※ 拡散する光線は目に届き難いので、知覚できません
※ 入射光線と拡散せずに射出する光線の角度は約52°です
下右図は下左図に示すディテクター(検出器)のエネルギー分布を示します
下側の光線束は拡散し、最上部の光線が拡散していない様子が確認できます


❍ 色分解の原因
下左図は僅かに離れた箇所に2本の光線が入射した状態です
観察者から見ると、その2本の光線の延長線上の接点に発光点があるよう観察されます
※ 主虹と比較して反射回数が1回多いので、副虹は長波長の光が内側、短波長の光が外側に見えます